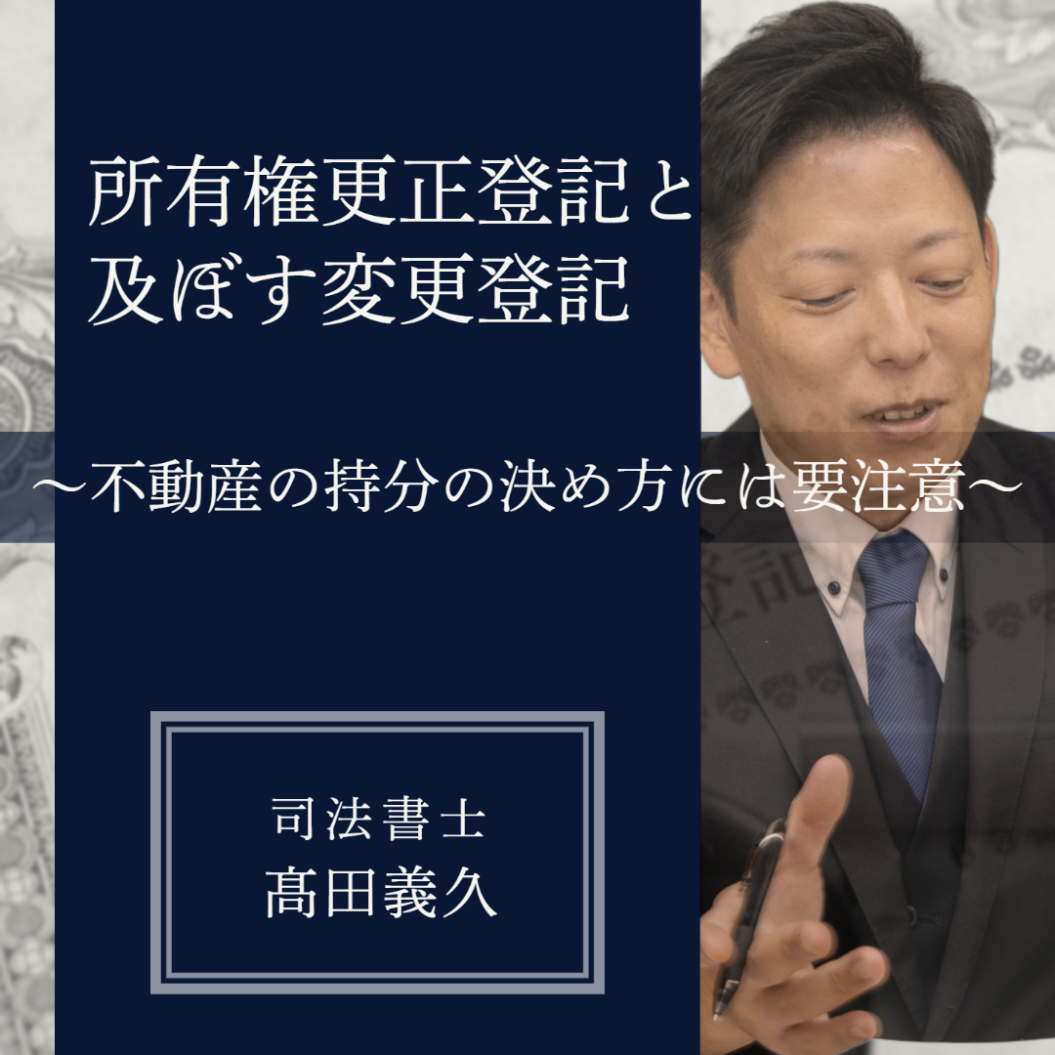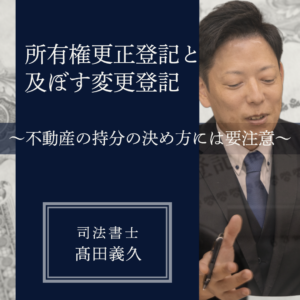
1.はじめに
今回の記事は、司法書士試験に合格して約10年になる司法書士が初めて経験した登記申請について記載しました。正直、タイトルからして、あまり読む気がしないと思いますが、司法書士または司法書士試験受験生の参考になればと思い、記載しました。
司法書士または司法書士試験受験生以外の方は、住宅ローンを使ってマイホームを購入する際に不動産の持分を間違うと面倒だ、ということをご理解頂ければと思います。
2.具体的事例
3.問題点
今回、私に依頼が来た時点で上記事例の登記は完了しており、建物の登記簿謄本を確認したところ、共有者AとB(持分2分の1ずつ)、債務者をAのみとする抵当権設定登記が記載されていました。
司法書士であれば、この登記簿謄本を見たとき、違和感を持つと思います。
共有で不動産を購入する場合、不動産の持分はそれぞれの出資割合(平たく言うと、共有者がどれだけお金を出したか)によって決めるべきものです。今回、Bは建物購入資金を出していないにもかかわらず建物の2分の1の持分を取得したことになり、AからBへ当該持分の贈与がなされたことになってしまいます。たとえ持分2分の1としても新築建物の贈与となると、ほぼ確実に贈与税の対象になってしまいます(贈与税は高い!)。また、上記事例ではAの住宅ローン控除にも影響が出てしまうため、二重に問題がある状態でした。
4.法律構成
上記事例では、税理士から贈与税及び住宅ローン控除の点で問題がある旨の指摘を受けたことから、私に依頼がありました。依頼内容は、共有から単有に変更して欲しいということでした。
ここで、司法書士としては、法律構成(登記原因の選択)として、①真正な登記名義の回復、②所有権更正のいずれかを検討すると思います。
そこで、以下、①・②のメリットとデメリットを記載します。
| メリット | デメリット | |
| ①真正な登記名義の回復 | 金融機関の関与が不要 |
登録免許税が高い
(税率1000分の20) |
| ②所有権更正 | 登録免許税が安い (一筆1,000円) |
金融機関の関与が必要
(金融機関の実印付承諾書が必要) |
今回、金融機関の協力が得られたことから、②所有権更正を選択しました。
ただし、ここで、錯誤を原因としてA・B共有からA単有に所有権更正登記を申請する場合、元々、金融機関がBの持分に対して設定していた抵当権の効力は錯誤によりAが取得する持分に対しては及ばない(元々の金融機関が設定していた抵当権の効力は当初Aが有していた持分2分の1に縮減される)ことになります。
当然、金融機関としては、所有権更正登記後も抵当権の効力を建物全体に設定する必要があるため、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記(いわゆる及ぼす変更登記)が必要になります。
なお、所有権更正登記に添付する金融機関の承諾書には、金融機関の実印を押印しなければならないため、金融機関の印鑑証明書が必要(3ヶ月の期間制限は無し)ですが、登記申請書に会社法人等番号を記載した時には、当該印鑑証明書の添付は省略することができます(不動産登記規則第50条第2項・第48条第1項第1号)。
もっとも、私は、当該金融機関と付き合いが無かったことから、印影照合のため、印鑑証明書を依頼しました。
5.感想
受験勉強以来触ることがなかった知識でしたので、登記が完了するまで不安でしたが、無事に完了し、ホッとしています。
不動産の持分の決め方については、ネットを検索すれば、たくさんの記事が出てきますが、意外に所有権更正とか及ぼす変更の記事はほとんど出てきませんでしたので、私自身の経験を元に記事にしてみました。この記事をご覧になられた方のお役に立つことができれば幸いです。
執筆・監修